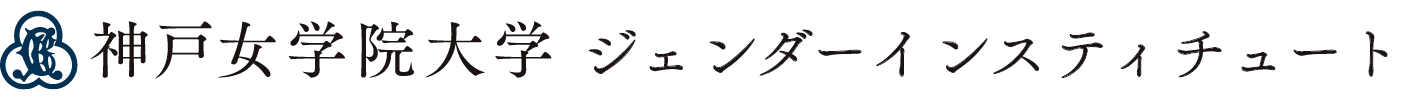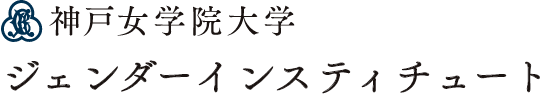2025.07.28 千里の道も一歩から(津上智実 名誉教授)
ジェンダーの規範は、人が安らって生きていく手助けにもなれば、一定の社会からの排除等の形で大きな妨げにもなる。身近なところでは日本の社会も緩やかに変わりつつある。休日の電車で子連れのお父さんたちを見る機会も増えたし、電車の運転手さんは男という常識も過去のものとなった。一方で政治とか大企業とか、大きなシステムになればなるほど女性が排除されていると感じるのも事実である。
ここでは、「京都賞」を例に考えてみよう。京都賞は、公益財団法人稲盛財団が1984年に創設した国際賞で、毎年、「先端技術部門」「基礎科学部門」「思想・芸術部門」の3部門4授賞対象分野の専門領域で選出された人物に、京都賞メダル、ディプロマと賞金1億円が贈られる。「思想・芸術」部門は、「思想・倫理」「映画・演劇」「美術」「音楽」の4分野で順に回すので、各分野の受賞は4年に1度という形になる。
過去の受賞者は京都賞のホームページに顔写真入りで掲載されて、何年に誰がどの分野で受賞したかが一目で分かる(https://www.kyotoprize.org/laureates/)。「思想・芸術」部門で女性の受賞者を探すと、「思想・倫理」は10人中3人(2012年のガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク、2016年のマーサ・クレイヴン・ヌスバウム、2025年のキャロル・ギリガン)、「映画・演劇」は10人中2人(2008年のピナ・バウシュ、2019年のアリアーヌ・ムヌーシュキン)、「美術」は10人中3人が女性(2014年の志村ふくみ、2018年のジョーン・ジョナス、2023年のナリニ・マラニ)なのに対して、「音楽」分野は10人中0人である。ちなみに同じく日本人の受賞者を探すと、「映画・演劇」には黒澤明(1994)、初代吉田玉男(2003)と坂東玉三郎(2011)、「美術」には安藤忠雄(2002)と志村ふくみ(2014)がいるが、「思想・倫理」と「音楽」分野はゼロである。
こうして見ると、「音楽」分野が一番偏っているように思われる。
「音楽」分野の受賞者は誰かと言えば、順にオリヴィエ・メシアン(1985)、ジョン・ケージ(1989)、ヴィトルト・ルトスワフスキ(1993)、イアニス・クセナキス(1997)、ジョルジュ・リゲティ(2001)、ニコラス・アーノンクール(2005)、ピエール・ブーレーズ(2009)、セシル・テイラー(2013)、リチャード・タラスキン(2017)と30年以上にわたって白人男性で占められてきた。ここには強いジェンダー・バイアスと白人優位主義が見え隠れしているのではないだろうか。その中で、2022年にインドのタブラー奏者ザーキル・フセインが受賞したのが快挙と言える。
思えば、アメリカの大統領も女性より黒人が先だった。京都賞の「音楽」分野で、日本人ないしはアジア人の女性が受賞するのは一体、いつの日のことか。
目を転じれば、映画の国際賞のアカデミー賞では、2015年と16年の主演・助演の男優・女優賞にノミネートされた40人全員が白人という状況から、2022年に中国系マレーシア人のミシェル・ヨー(60)がアジア人として初の主演女優賞を受賞するという動きへの変化が見られる。もっともこれはジェンダーギャップ指数43位のアメリカでの話で、同118位の日本では望むべくもないという声も聞こえてきそうだが、諦めてしまっては始まらない。気がついた人間から声を上げていく他ないだろう。道は遠い。が、千里の道も一歩からである。
執筆者(執筆時点):
津上智実 名誉教授 (音楽学)
女性学インスティチュート(新名称:ジェンダーインスティチュート)
11代ディレクター(2016.4.1~2020.3.31)
最新記事
-
2026.01.07
同性婚訴訟の行方(文学部 教授 米田真澄) -
2025.07.28
千里の道も一歩から(津上智実 名誉教授) -
2025.03.18
生理前と生理中のつらい症状をやわらげる対処法(人間科学部 教授 高岡素子) -
2024.12.24
ヒジュラ〜「第三の性(The Third Gender)」と呼ばれる人たち(国際学部 准教授 南出 和余) -
2024.08.06
同性愛者は犯罪者?(文学部 教授 金田 知子)